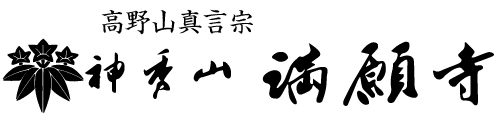金 堂

本尊は阿弥陀如来。元 円覚院の常行堂にあったと伝えられています。昭和58年3月から全面解体修理を施し昭和60年4月に落慶法要(らっけいほうよう)を挙行しました。
内陣の宮殿



内陣の宮殿(くうでん=本尊の厨子)は室町時代後期に造られたものと判明しました。県指定文化財/総棟高3.161m
金堂に安置。ほまば完全な唐様(禅宗様)でまとまっている。弘治四年(1558)、永禄二年(1559)の墨書があり、室町時代末期の標識建築として極めて貴重である。
開眼阿弥陀如来

内陣の宮殿(くうでん=本尊の厨子)は室町時代後期に造られたものと判明しました。県指定文化財/総棟高3.161m
金堂に安置。ほまば完全な唐様(禅宗様)でまとまっている。弘治四年(1558)、永禄二年(1559)の墨書があり、室町時代末期の標識建築として極めて貴重である。
十一面観音

平安時代後期の作 県指定文化財 /像高159.1cm 金堂に安置。ほっそりとした長身の像で、面相はおだやかである。
薬師如来

平安時代作 像高 70cm 薬師如来は東方浄瑠璃世界の教主で、無明の病を治す法薬を与える医薬の仏として信仰を集めています。
井上正(元 京都博物館)著「古佛彫刻のイコノロジー」(昭和61年10月発行)に詳しい解説文の記載があります。
聖観音菩薩

平安時代の作 県指定文化財 / 像高166.3cm 金堂に安置。肩の張った重厚な肉取りに平安時代前期の古様をみせるが、面相は穏やかである。